一級建築士の星悠真です。
冬になると、吸気口(換気口)から冷たい風がスースー入ってきて、マンションの部屋がなかなか暖まらないことがありませんか?
実は、「寒いから吸気口を閉じる」という行為はNGです。換気が滞って結露やカビ、健康被害を引き起こす恐れがあります。
この記事では、一級建築士の視点から、吸気口を閉じずに寒さを和らげる3つの具体的な方法を解説します。実際にマンションに住んでいる私も実践している方法です。
- 暖房とサーキュレーターで空気を循環させる
- 家具の配置を工夫して冷気を感じにくくする
- 窓まわりの断熱対策で部屋全体の保温力を上げる
この3つを実践すれば、吸気口を閉じなくても、部屋を暖かく保つことができます。

あなたの寒さの悩みを、建築のプロとしてしっかり解決していきます。
マンションの吸気口(換気口)が寒い理由とは?

吸気口(換気口)が寒い理由は、建物の「換気構造」と「断熱性能」にあります。
これは”建物の仕組み”による問題です。
吸気口は「24時間換気システム」の入口
マンションでは、24時間換気システムが建築基準法で義務づけられています。
その仕組みの「入口」が吸気口で、外から新鮮な空気を取り入れています。

冬は外気が冷たいため、吸気口から入ってくる空気も当然冷たくなります。つまり、構造上どうしても冷気が入りやすいのです。
寒さを感じやすい部屋の特徴
部屋が次のような条件に当てはまるなら、吸気口の冷気を感じやすい状態かもしれません。
- 北向きの部屋で日当たりが悪い
- 吸気口のすぐ近くにベッドやソファがある
- 築年数が古く、壁や窓の断熱性能が低い
こうした条件が重なると、吸気口から入る外気が部屋全体の温度を下げてしまいます。
マンションの吸気口(換気口)を閉じても大丈夫?

吸気口(換気口)を閉じるのは避けましょう。
寒さを防いだつもりでも、健康や建物へのリスクが高まります。
換気バランスが崩れ、結露やカビの原因に
吸気口を閉じると、室内の空気が外に出る一方で、新しい空気が入ってこなくなります。
その結果、部屋の中が負圧になり、壁やサッシの隙間から空気が無理に入り込んだりします。
このとき、温度差によって結露が発生します。

特に北側の壁や家具の裏は湿気がこもりやすく、カビが生えやすくなります。
二酸化炭素がこもるリスクも
空気が入れ替わらない状態が続くと、室内のCO₂濃度が上昇します。
特に寝室では、朝起きたときに頭が重い、だるいと感じる原因にもなります。吸気口を閉じると、一時的に暖かく感じても、長期的には体調や建物の健康を損なう可能性があります。
【対策①】暖房+サーキュレーターで空気を循環させる
吸気口からの冷気が寒いと感じる一番の理由は、空気のムラです。
暖かい空気が上に、冷たい空気が下に溜まり、温度差が生まれています。
サーキュレーターで空気の層をなくす

image : Amazon
暖房をつけても足元が寒いのは、暖気が天井付近に溜まっているからです。
サーキュレーターを使えば、その暖気を全体に回し、空気を均一にできます。
部屋全体の温度差をなくすことで、吸気口の冷気を感じにくくなります。
設置のポイント
サーキュレーターは吸気口のある壁の反対側に置き、天井に向けて風を送ります。
直接体に風を当てず、空気を動かす意識で使いましょう。また、エアコンの風が偏らないように、部屋の対角線上に設置すると効率が上がります。
光熱費も下げられる

空気が循環すると、部屋全体が均一に暖まります。
暖房の設定温度を1〜2℃下げても快適に感じるため、光熱費の節約にもつながります。

サーキュレーターは省エネで動作するので、実はコスパの良い寒さ対策なのです。
サーキュレーターの選び方
「サーキュレーターの種類が多すぎて何を買えばいいか分からない…」と悩んでいませんか?
以下の記事で6畳〜30畳までの部屋の広さに応じたサーキュレーターの選び方と、おすすめモデル7選を紹介しています。是非参考にしてください。
サーキュレーターは部屋の広さで決める!選び方と厳選7選|一級建築士厳選【2026年版】
【体験談】サーキュレーターで電気代が下がりました!

我が家も、2年前からサーキュレーターを導入しています。
私の場合、冬のリビングでの暖房の快適温度は、サーキュレーターなしでは24℃です。
しかし、サーキュレーターと暖房を併用して暖気を天井から床に流すように促すことで、暖房の設定温度を22℃まで下げることができました。

我が家の条件の場合、導入前後で冬の電気代が1か月1,500円程度下がりました。
【対策②】家具の配置を工夫して冷気を感じにくくする
家具の位置によっても寒さの感じ方は変わります。
吸気口からの冷気が体に直接当たる位置に家具を置いていると、余計に寒さを感じます。
吸気口の前にベッドやソファを置かない

吸気口の前に寝具やソファを置くと、冷気が体に当たります。
特に寝ている間は、長時間冷気を浴び続けることになり、体調を崩す原因になります。
ベッドやソファは吸気口から30cm以上離すようにしましょう。難しい場合は、吸気口の前に背の低い棚や観葉植物を置いて、風をやわらげるのも有効です。

我が家の場合は、吸気口付近はテレビ置き場にして居住スペースを設けていません。
床の冷気対策も忘れずに

image : Amazon
吸気口から入った冷気は床に沿って流れます。
床が冷えると足元から体温が奪われ、全身が寒く感じます。
ラグやカーペットを敷くだけでも、体感温度は上がります。また、厚手のラグを選べば断熱効果も高まり、見た目にも暖かい印象になります。
【対策③】窓まわりの断熱性能を上げて、部屋全体を暖かく保つ
吸気口だけでなく、窓まわりも大きな冷気の侵入ポイントです。特にマンションでは外壁がコンクリートでも、窓部分から熱が逃げやすくなっています。
断熱カーテン+カーテンライナーで冷気の侵入を防ぐ

image : Amazon

image : Amazon
厚手の断熱カーテンを使うと、窓からの冷気を大幅にカットできます。
まずは「遮熱・断熱」と表記された厚手のカーテンを選んでください。 さらに、ビニール製の「カーテンライナー」を併用することがプロの推奨です。
ライナーを床に10cmほど垂らすことで、窓からの冷気が室内に侵入する隙間を塞ぎます。 このわずかな隙間が空気層となり断熱材の代わりになります。
窓に断熱シートを貼る

image : Amazon
ガラスに直接貼る断熱シートは、空気の粒を閉じ込めた構造で熱の伝わりを遅らせます。 梱包用のプチプチに似ていますが、住宅用は紫外線に強く劣化しにくいのが特徴です。
窓ガラスに直接貼ることで、外気との間に空気層ができ、熱の伝わりを防ぎます。

貼るだけで効果を感じられる、低コストで実践できる方法です。
古いマンションはサッシの隙間テープで対策

image : Amazon
築年数が経ったマンションでは、サッシのゴムパッキンが劣化して隙間風が入りやすくなっています。
その場合は、サッシのすき間に隙間テープを貼るだけでも効果があります。
隙間風が減ると、吸気口以外からの冷気の流入が抑えられ、部屋全体の保温性能が向上します。これも簡単にできるDIY断熱のひとつです。
まとめ|吸気口(換気口)を閉じずに“空気を動かして・断熱して”暖かい冬を

吸気口を閉じると、一時的には暖かく感じても、結露やカビ、換気不良などのリスクを招きます。
寒さを根本から解決するには、空気を動かし、断熱性能を上げることが大切です。
今日からできる安全で効果的な対策は次の3つです。
- 暖房+サーキュレーターで空気を循環させる
- 家具の配置を工夫して冷気を感じにくくする
- 窓まわりの断熱対策で保温力を高める
この3つを実践すれば、吸気口を閉じなくても部屋全体が暖かくなり、快適に過ごせます。今日から少しの工夫で、吸気口を閉じずに暖かく快適な住まいをつくりましょう!

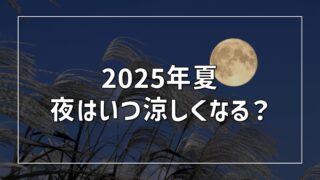
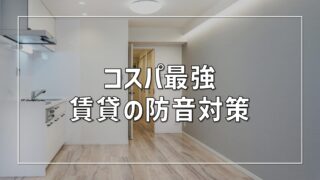
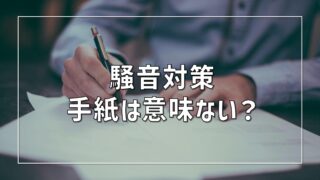
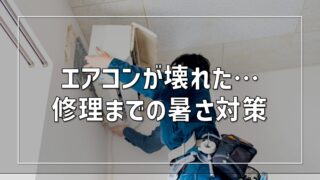

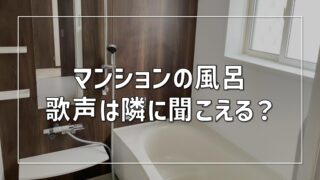

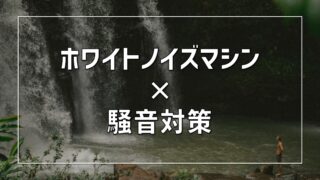
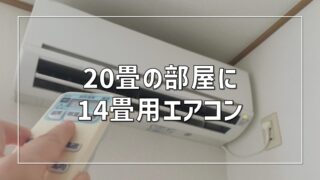
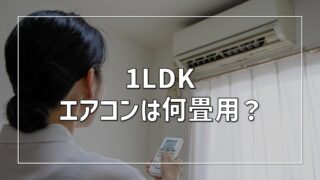
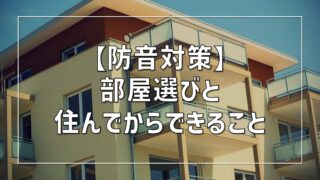


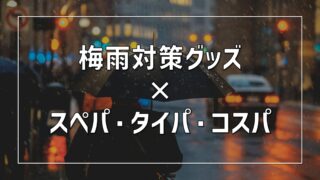
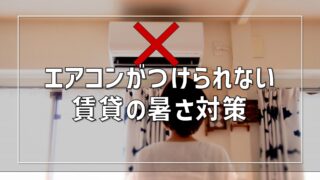
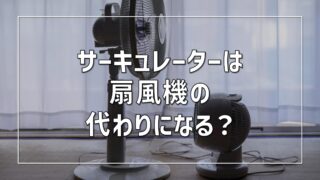
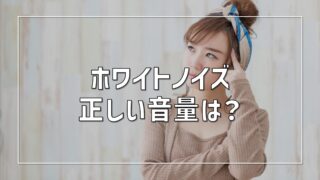
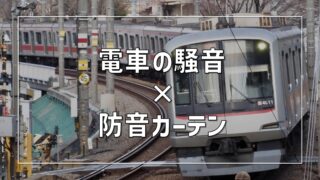
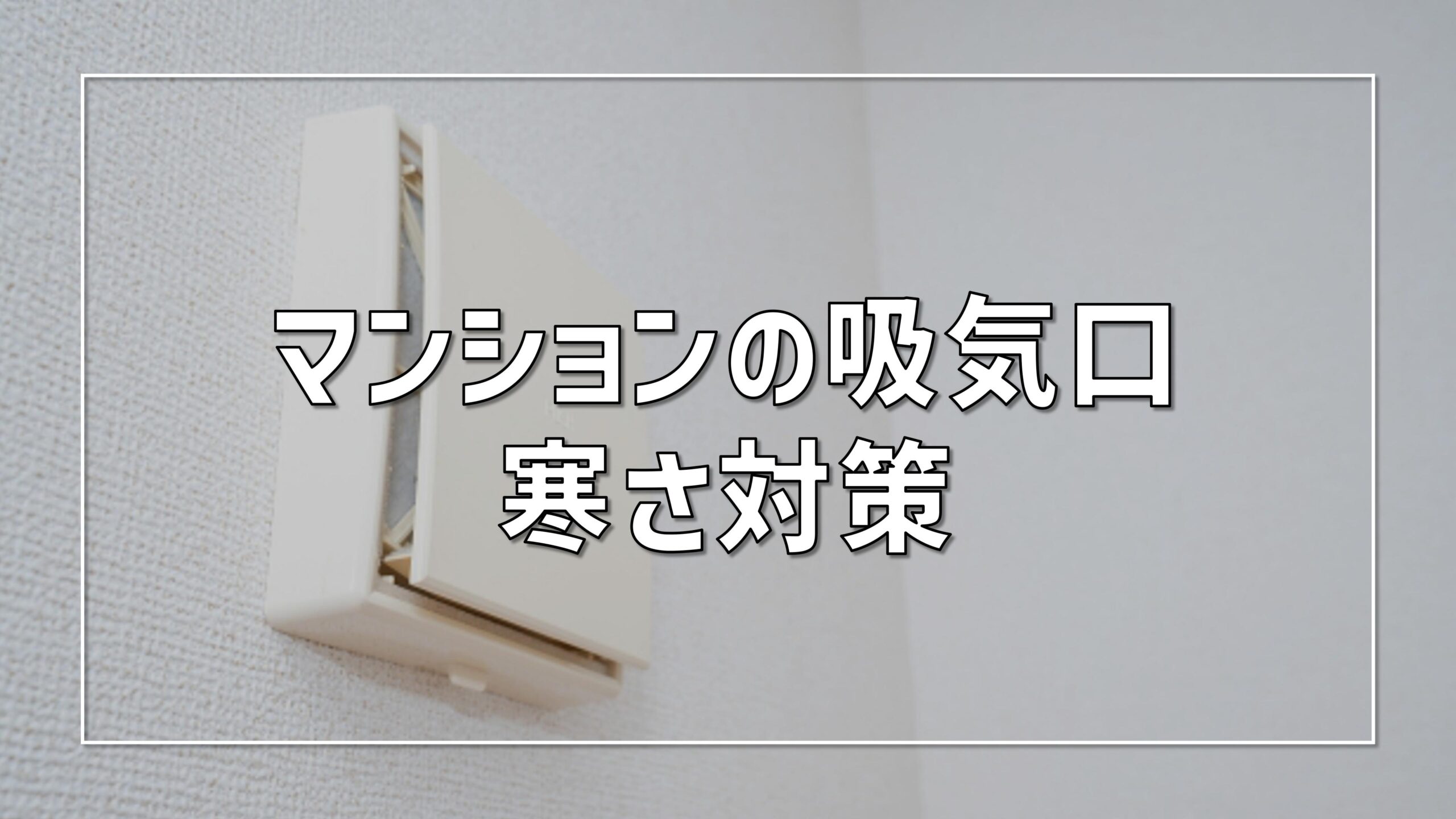









コメント